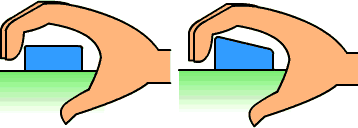OPEN
1.主旨と説明
2.用語集
3.基本操作法
4.我輩所有機
5.カメラ雑文
6.写真置き場
7.テーマ別写真
8.リンク
9.掲示板
10.アンケート
11.その他企画
12.カタログ
カメラ雑文
|
[331] 2002年01月30日(水)
「ハンドグリップ試用レポート」
まだカメラ雑文が「単なる日記」であった頃、雑文002にて「Nikon F3用の軽量ワインダーが欲しい」と書いた。巻上げ速度を要求されない撮影には軽量なワインダーが良い。
しかし、軽量なるワインダーを欲するのは別の動機もある。それは、グリップとしての要求だ。  我輩は昔、「Canon AE-1+P」を使用していた。その頃流行しはじめたモータードライブを手に入れようと貯金を始めたのだが、今一歩及ばず、「モータードライブMA」のグリップ部だけしか買えなかった。
我輩は昔、「Canon AE-1+P」を使用していた。その頃流行しはじめたモータードライブを手に入れようと貯金を始めたのだが、今一歩及ばず、「モータードライブMA」のグリップ部だけしか買えなかった。電源部が無く、当然ながら巻上げは手動である。しかもモーターとギアのトルクが掛かって巻上げは少し重かった。しかし、それでもグリップ感が飛躍的に向上し、撮影が楽になったように記憶している。 さて、インターネットの情報を色々と辿っていると、個人でグリップを製作しているというサイトが幾つか見付かる。その中で、「digital camera workshop」というサイトと縁があり、今回、そこで製作されたハンドグリップをモニター使用することになった。今回の雑文は、そのレポートいうことになる。 ここで製作されるグリップは主にデジタルカメラ用であるが、銀塩カメラ用の注文も多くあるそうで、「Nikon FE」用や「Canon FT-b」用などの対応もある。 当初、我輩には「Canon FT-b」用しか選択肢は無いと考えていたのだが、よく考えると「Nikon FE」用として作られたグリップはモータードライブ共用の「Nikon FA」も対応するはず。もしFAに付くならば、稼働率の高いFAにグリップを付けたい。 グリップの素材は、「ラバー」、「紫檀」、「黒檀」、「バーロッサ」から選ぶことが出来る。我輩は色合いを重視したため、紫檀を使って製作をお願いした。  数週間後、それは我輩の手元に届いた。
数週間後、それは我輩の手元に届いた。早速、FAに装着してみる。FE用に作られたグリップであるが、確かにFAにもピッタリと装着出来た。まずは一安心というところか。 紫檀の色合いは実際に見てもなかなか渋い。高級オーディオのウッドパネルのような感じがある。これは使い込むにつれて更に良い色合いとなるという。そしてそれを支えているのがアルミ素材で、鈍い光沢がそれっぽい。 我輩のFAはブラックボディであるが、もしクロームボディならばアルミの色に溶け込み、より一層の一体感があっただろうと予想する。 表面は良くポリッシュ(研磨)され、木部との段差が全く感じられないのが驚く。目をつぶってなぞると、その境目を知るのは温度変化のみとなる。 面取りもしっかりと行われており、金属部には鋭いエッジが無い。これならば手を痛めることも、また衣服に引っかけることも無い。仕上げには手間を掛けている。 木材の加工ならばシロウトでも何とかなろうが、金属の加工はそれなりの設備が無ければ難しい。それだけでもこのグリップの価値があると言えよう。  元々、FAには着脱式のグリップが付属している。しかし、それはグリップと言うよりも「盛り上がり」と言ったほうが良いくらいの小さなもの。無いよりもマシという程度しかない。それは、「Canon AE-1+P」の場合も同じである。
元々、FAには着脱式のグリップが付属している。しかし、それはグリップと言うよりも「盛り上がり」と言ったほうが良いくらいの小さなもの。無いよりもマシという程度しかない。それは、「Canon AE-1+P」の場合も同じである。それに対し、今回のグリップは指が回り込むのが良い。多少、我輩の手には小さいという感じはするが、片手でカメラを提げていても不安が無いくらいのグリップ感がある。 手巻き式のカメラというのは、右手親指で巻上げレバーを操作するようになっている。しかし、右手親指はカメラを捕まえておくには重要な支えでもあるから、片手でホールドしながら巻上げるというのは難しい。もしグリップがあれば、親指の負担を軽減させ、片手で巻上げを行うことも可能となろう。 スナップ写真では撮影時こそ両手で構えるものの、その合間には片手でカメラを提げることが多い。その間にフィルムを巻上げ、次に構えた時には撮影準備を完了させている。確かにこれは、分割巻上げが可能なカメラであれば楽であるが、FAは分割巻上げが出来ないためそれが難しい。モータードライブを使わないスナップ撮影において、このようなグリップの存在は撮影リズムを維持するのに役立つ。  グリップの固定は、カメラ底部の三脚用ネジ穴にグリップのネジを締めて行うオーソドックスな方式。グリップを装着したカメラを三脚等に固定するには、グリップネジの底面にあるネジ穴を使うことになるのかも知れないが、このネジ穴は浅いので三脚を選ぶだろう。また、その場合は接地面積が狭いため安定は難しい。
グリップの固定は、カメラ底部の三脚用ネジ穴にグリップのネジを締めて行うオーソドックスな方式。グリップを装着したカメラを三脚等に固定するには、グリップネジの底面にあるネジ穴を使うことになるのかも知れないが、このネジ穴は浅いので三脚を選ぶだろう。また、その場合は接地面積が狭いため安定は難しい。グリップネジの横にもネジが切ってあるのだが、これはグリップネジの位置に近すぎて干渉するため、三脚固定用としては使えない。また、他のアイデアで使うとすれば、ネジ穴が貫通しているため、深いネジを使うとカメラ底部に傷を付ける恐れがあるので、注意が必要。 ただ、グリップを使う時には三脚など不要であるから、特に気にする必要も無かろう。どうしても三脚が使いたければ、素直にグリップを外せば良い話。  グリップがカメラに接する部分には、全面にラバーシートが貼られており、カメラ側を傷付けることは無い。
片手でグリップを持って提げて巻上げ動作を行った時、グリップを握る力が大きくなるためか、微妙ではあるが「しなる」のを何となく感ずる。これは、グリップのネック部分が細くなっているためと思われるが、スナップ的な装備では全く問題は無い。
グリップがカメラに接する部分には、全面にラバーシートが貼られており、カメラ側を傷付けることは無い。
片手でグリップを持って提げて巻上げ動作を行った時、グリップを握る力が大きくなるためか、微妙ではあるが「しなる」のを何となく感ずる。これは、グリップのネック部分が細くなっているためと思われるが、スナップ的な装備では全く問題は無い。このグリップはスナップ撮影では十分と言えよう。カメラに付けっぱなしにしておいても苦にならぬグリップであるから、万能を狙って更に大きくすると、かえって利点を失うことにもなりかねない。大口径レンズや長焦点レンズを片手でぶら下げるような場面もあまり無いと思うため、それほど気にする問題ではないかも知れない。 しかし人間とは欲が深いもので、もし今後の改良点を望むならば、更なるグリップ感向上を期待したい。 グリップというのは、適度な直線があればそこが指掛かりとなって持ち易さを与える。そういう意味ではこのグリップは良い。だがそれも、大きさによる限界が当然ある。 あまり大きくせずにグリップ感を向上させるには、指の第一関節辺りで引っかけられるようにグリップの指掛かりの厚みがもう少しあれば良いと感ずる(下図右側)。その分、手のひらに近い部分は薄くても大丈夫であろう。
以上、少々うるさいレポートだったが、非常に有用なグリップなだけに、注文が大きくなるのは仕方が無い。
(※今回のレポートで触れた点については、改良を検討するとの回答を頂いた。) 最後になったが、今回グリップを製作しモニターの機会を与えて頂いた「digital camera workshop」殿にはお礼を申し上げたい。 |